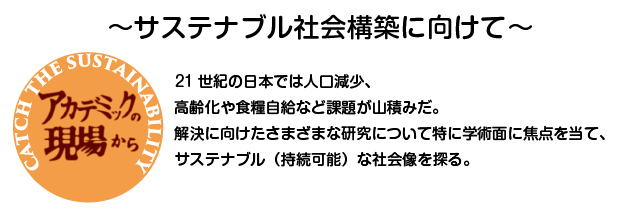
サステナブル社会とは
sustainable:「持続可能な」の意味。環境保護と自然開発を共存させ、
持続可能な経済成長を目指す社会のこと。
第11回
学術研究が開くサステナブル社会
これまで登場した研究現場
化石燃料の使用で排出されるガスが地球温暖化を進行させると問題になっているが、そもそもその燃料資源の埋蔵量は有限で、いつまでもサステナブル(持続可能)に利用はできない。では現代社会を支えるエネルギーは何に頼ればいいのか。社会の持続的発展を脅かす要素はほかにも、急激な都市化、少子高齢化、減退する第一次産業、気象災害など数知れない。サステナブル社会構築の阻害要因を打破してくれる知恵を求め、これまで大学など学術研究の場から10回にわたるレポートを届けてきた。
研究テーマに多く見られたのは地方創生や地域の活性化などの分野に関連するという特徴だ。地産地消はその有効な手立てになるが、第1回で紹介した住民参加型で広がる小水力発電も、第5回掲載の再生可能エネルギー(再エネ)を家庭でもつくれるようになる小型風力発電も、消費するその場所で必要なものを生産する研究だった。
第2回のESD(持続可能な開発のための教育)ではまさに「地域創生」を重視し、衰退が懸念される地域から、自然や文化、人材などを発掘し利用する取り組みが進められていた。第7回は環境問題が起きている地域や現場に寄り添い解決していく臨床環境学、第3回は山村再生、それぞれ意欲的な教授のもと学生らが実践の活動を続けていた。第4回の日本版CCRCは健康なうちに入居する高齢者施設。新しい仕組みのコミュニティを地方に創設し、都市部で不足が予想される介護施設の解消も狙う。これらの研究が示唆しているのは、一極集中の都市よりも、自立した地域が有機的につながり合う形のほうが、サステナブル社会にとって高い親和性を示すということだろう。
その他、大手メーカーが参入しにくい路線バスの電動化や局地的なゲリラ豪雨の予測精度向上といった技術開発に関する研究も取り上げた。水産資源の永続的な確保を目指すサステナブルな漁業、ごみ問題が学べる絵本を制作しインドの小学校に寄贈したデザインでの環境貢献などユニークな学術研究の場からも報告してきた。
サステナブル社会を切り開けるようなアカデミックの現場があれば、今後も本欄で紹介していく予定だ。