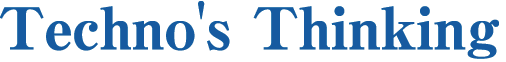
日本テクノは電気の安心・安全、安定供給を第一に考えるとともに、
「経済成長と省エネの両立」に向け、
日々新たな商品の創造とサービスの充実を図っております。
このコーナーでは、その時々の社会事情における企業姿勢を紹介しています。
自由化の根底には安定供給の思想がある
その原点に立ち返る
2016年4月に電力の小売り市場が全面自由化された。自由化が進められた背景の1つには、東日本大震災後に起きた電力不足問題への対応があげられる。当時、電力が不足したのは全国的にみれば一部の地域だった。周波数の違いなど送配電網(地域同士をつなぐ連系線)の問題で、ほかの地域から電力が思うように供給できず、同じ日本国内で電力に余裕のある地域と不足するエリアとが混在する事態に陥った。そのアンバランスな状況を、市場の自由化で緩和しようという期待である。
自由化が進展していけば、地域を超えた取引が盛んになる。それを下支えするには、しっかりした地域間連系線が必要になる。連系線の整備には膨大な費用がかかるが、活性化した自由市場が背中を押す役目を果たしてくれる。つまり、自由化の根底思想には、どの地域にも電力を安定供給するという社会的要請が含まれている。
だが現在、後述するエリアプライスの高騰など、自由化を取り巻く新たな課題が生じている。
ここでエリアプライスについて論じる前に、自由化推進に大きな存在感を示す「日本卸電力取引所(JEPX)」について説明しておく。おおまかにいえば、個々の需要家に電力を売りたい企業が、販売する商品(つまり電力)を仕入れる場所。その商品は発電をした事業者が市場に並べる。もちろん実際の取引はインターネットを介した情報のやり取りで行われる。
JEPXは電力会社や新電力などからの拠出金により2003年に設立された。取引開始は2005年4月から。メインの取引は「一日前市場(スポット市場)」と呼ばれるものだ。ここでは小売り事業者などが、翌日の需要予測をもとに、電力の買い注文を入れ、発電事業者は設備の状況に応じた供給計画で売り注文を入れる。1日を48分割した30分単位で取引され、約定価格は「ブラインド・シングルプライス オークション方式」で決定される。他の参加者の動向が開示されない状態で入札し、締め切り後、取引所がすべての入札を合成して需給カーブが均衡する点で約定価格を決定する。全国統一の約定価格で売買できるシングルプライスである。
ただし需給がエリアをまたぐ場合には、連系線の空き容量によって統一価格にならないことがある。現在ある連系線には流せる電力量に限りがあり、それを超えるときには、エリアごとに入札を合成し直し、約定価格を決めるからだ。これを市場分断処理といい、その価格が、先に示した「エリアプライス」である。
そのエリアプライスが、しばしば市場関係者も驚くような高値になっている。自由化が進むにつれ、地域をつなぐ連系線は混雑をきわめ、緊急時の容量を確保すると、空きがないともいわれる。それが市場分断処理されたエリアプライスが出現する主な原因である。
連系線の整備は、一朝一夕にできるものではない。そのために、新たな機関が設立され、よりよい環境整備や監視機能の強化がなされている昨今だ。連系線の増強や系統運用ルールの見直しも行われている。だが、需要と供給力の偏在を解消しなければ根本的な解決は難しい。問題を解決する有力な方法の1つは、市場の厚みを増し、効率的市場を形成することであろう。
そんな過渡的状況にある現在、電力システム改革の旗の下で行われる自由化の目的や思想を再度見つめ直してみたい。