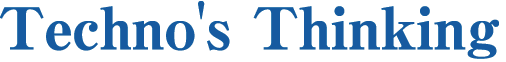
日本テクノは電気の安心・安全、安定供給を第一に考えるとともに、
「経済成長と省エネの両立」に向け、
日々新たな商品の創造とサービスの充実を図っております。
このコーナーでは、その時々の社会事情における企業姿勢を紹介しています。
小売り全面自由化開始
これまでの日本の電力事情を振り返る
今年4月から電力小売りが全面自由化される。今回は、その大きな転換期を前に、電力が日本においてどのような道をたどってきたのか振り返っていく。
日本の電力システムは世界的にも完成度が高く、1軒あたりの年間停電回数は0.13回である。自然災害や突発事故以外ではほとんど停電のない国だ。停電後の復旧スピードも早く、古くは広島に原子爆弾が投下された3日後には路面電車が動いていた。東日本大震災でも復旧は早く、当社も1週間で800件の緊急応動を行い、多くの事業場を復旧させた。すべてを完了するまで3週間だった。
電力システムの始まりは、1879年にエジソンが炭素フィラメントによる白熱電球を発明し、照明が大きな注目を集めたころだろう。1882年には銀座で電灯がともり、翌年は日本初の電力会社・東京電燈会社が発足。1899年に沖縄を除く全国9地域に電灯会社が揃った。電源開発が進んで一般家庭にも電灯が広がり1927年には普及率は87%に達する。そして戦時下の1939年、日本発送電株式会社が設立され電力は国の管理となる。
戦後の1951年、日本発送電株式会社は解体。発電設備を9配電会社に移管し、発送電一貫体制が確立した。この体制は、その後の高度成長期、オイルショック、プラザ合意、バブル崩壊など、さまざまな環境下で日本経済を支え続けた。
その第一次オイルショック時には電力使用制限令が出された。これを契機に省エネを推進する国策に企業が技術革新で応え、電化製品や自動車など世界をしのぐ省エネ技術が発展していく。
時は移りJRやNTTなどインフラの民営化と自由化の大きな流れの中で、電力の自由化も進められていく。2000年に電力量の約26%を占める大規模工場やデパートなどの特別高圧(2000㌔㍗以上)、2004年に中規模工場やスーパーなどの高圧の一部(500㌔㍗以上2000㌔㍗未満)が自由化された。
さらに2005年、小規模工場などの高圧(50㌔㍗以上500㌔㍗未満)も自由化され、これにより販売電力量の60%の市場が開放された。当社は、この高圧部門への電力供給を2009年6月より東京電力管内にて始めている。この流れを締めくくるのが、今年の全面自由化である。
電力市場だけでなく発電の方法も時代ごとに移り変わった。
日本初の火力発電所は1887年、日本橋茅場町にできた。日本初の水力発電所は1891年、京都市が琵琶湖疏水を利用して建設した。その後、山が険しく川の落差が大きい日本の地形では水力発電が主流となっていく。1962年度に逆転するまで火力は水力の補助的な役割だったが、その後は火力が主流となった。火力の燃料は、当初の石炭から石油へ変化。オイルショック後にはLNGが急速に伸びている。
日本で最初の原子力発電は1963年。その後、依存度は高まり1985年には発電比率が23.7%になった。京都議定書が採択された1997年のころはすでに30%を超えていた。その状況下で東日本大震災が起き、今日に至っている。
ここまで、電力システムの転換期に際し、日本の電力事情の変遷を簡単に振り返ってみた。より詳しい内容は弊社の編んだ『イチから学ぼう デンキのキホン』(丸善出版)に記している。興味があれば参照いただきたい。