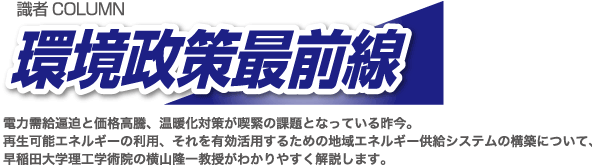
再生可能エネルギーの導入拡大へ
早期の「足止め」解消を期待
九州電力は再生可能エネルギーによる発電設備の接続申し込みを、2014年9月25日から数カ月間にわたり管内全域で保留すると発表し、東北、四国、北海道など他の電力会社も追随した。沖縄電力も接続可能量の上限超過を発表した。固定価格買い取り制度(FIT)によって太陽光発電が急増し、電力の需給バランスが崩れる可能性が生じたためとしている。
これらは電力安定供給と品質維持を目標とする電力会社の見解として理解はできる。だが、再生可能エネルギー導入を最大限加速するとした日本のエネルギー基本計画の意には反している。
特に福島県では、復興を成し遂げるため再生可能エネルギーの飛躍的推進を柱と位置づけその「先駆けの地」の実現を目指してきた。先のエネルギー基本計画でも福島の再生可能エネルギー産業拠点化を目指すと明記され、福島復興再生特別措置法第79条には財政上の措置その他の措置を講ずるべき国の責務も記されるなど、重要施策として積極的な推進が図られてきたところである。その矢先の回答保留、当然、反発の声は強い。
福島県は、電力会社による系統接続保留の決定が再生可能エネルギー推進と産業復興の根幹を揺るがす重大な問題だとして行政当局へ提言書を提出する構えだ。論拠は実際に運転開始している設備が少ないこと。東北電力管内の太陽光の設備認定は1073万kW(2014年5月末)だが、そのうち運転を開始したのは63万kWで、わずか5.8%。その段階での保留措置は妥当性に欠くと指摘。また、発電設備の建設にめどが立たないまま、認定だけを受けている空押さえの事業者の存在が、健全な新規事業を妨げているとも異議を唱える。
こうした事態に現在、経済産業省ではそれぞれの電力会社における接続可能量の検証を進めている。2014年11月5日の会合では、再生可能エネルギーの最大限の導入を実現するための論点として、①再エネのバランスある導入を巡る現状の制度とルール②再エネの調達価格③設備認定の取消・失効による対応④運転前の出力変更への対応⑤運転後の出力変更への対応⑥調達価格の決定時点の再検討⑦地方自治体への情報提供、などを示し、認定取り消しも含めた議論がなされた。
多くの県民や企業が事業実現を目前に「足止め」され、県内経済全体への影響は計り知れない。福島県の復興に水を差す深刻な事態であり、国の重要施策とも大きく矛盾する。早期の解決を期待したい。