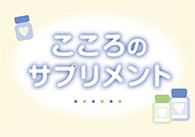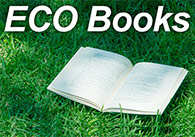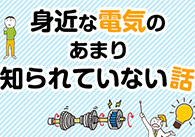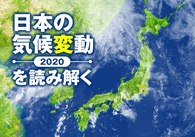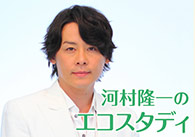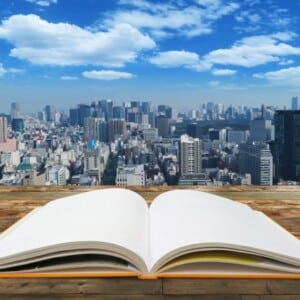食品だけじゃない!「発酵技術」がつくる持続可能な社会

発酵食品にはさまざまな種類があり、私たちがよく口にする豆腐、味噌、ヨーグルトなど、和食、洋食、中華のメニューで活躍する食材がたくさんあります。また発酵飲料は、日本酒、ワイン、ビール、焼酎、ウイスキー、紅茶、ウーロン茶など、アルコールからソフトドリンクまで幅広く、非常に身近な存在ですが、そもそも「発酵」とはどういう化学変化かご存知でしょうか。
発酵とは?

「発酵」とは、「微生物がもつ酵素によって物質が分解された結果、人間にとって有益なものができること」です。ここでいう微生物とは、主に細菌、酵母、カビをさします。細菌やカビという言葉に抵抗を感じる方もいるかと思いますが、細菌にはお酢づくりに必要な「酢酸菌」、ヨーグルトなどに使われる「乳酸菌」などがあります。カビには味噌や醤油などの発酵調味料づくりに欠かせない「麹菌」などといった、人間にとって良い働きをするものが多数存在するのです。この発酵作用を応用した技術は発酵食品だけでなく、社会のさまざまな分野で活用されています。
関連コラムはこちら

至福の1杯を飲むために、環境にやさしいビールについて考えよう!https://econews.jp/column/sustainable/12003/
(サステナブルノート2024.08.21)
未来の食料問題に備えた研究開発

近い将来、世界中で慢性的な食料不足が起こることが危ぶまれています。2017年に国連が発表した「世界人口予測2017年改定版」によると、現在76億人の世界人口は、2030年までに86億人、2050年に98億人にもなり、現在と比べて60%も食料生産を増やす必要があると推定されています。その一方で、食料を増産するための土地や水には限りがあり、毎年のように起こる異常気象の被害で、農作物の不作が起こっています。飢餓人口が増えることも懸念されているなかで、食料が当たり前のようにある時代ではなくなる可能性があります。こうした現状・予測をふまえ、世界では発酵技術を応用した新技術の開発が進められています。
発酵技術がブドウ糖をつくる
食料のムダを減らすため、発酵を使って食べられない、または食べにくいものを食べられるようにするという研究が始まりました。そのひとつが落ち葉やおがくずなどの未利用資源を分解し、人間が生きていくうえで最低限必要な栄養・ブドウ糖をつくろうという試みです。地球上には繊維分解酵素「セルラーゼ」を持つ強い糸状菌(しじょうきん)がたくさん発見されており、この微生物の遺伝子を組み換えることで、未利用資源をブドウ糖に変える菌をつくります。そしてそれをもとに食べ物を生み出そうというものです。
代替タンパク質をつくる「精密発酵」
また、タンパク質も私たちの体の水分を除いた重量の約半分を構成している、生きていくために欠かせない重要な栄養素。世界規模で一人あたりの肉や魚の消費量が増加し続ける一方で、現状の畜産や養殖は生産物の何倍もの穀物や魚粉によって賄われているため、2030年には世界でタンパク質の供給が需要に追いつかなくなると推測されています。食料とタンパク質に対する需要は増加する一方。「タンパク質危機(protein crisis)」と呼ばれる深刻な状況です。
そこで地球にやさしく、畜産だけに依存せずに食料を安定供給できるフードテック(※)が注目されるようになりました。なかでも最近特に注目されているのが「精密発酵」技術。精密発酵とは食品そのものをつくるのではなく、微生物を使って特定の機能性成分を生成させることをいいます。微生物につくりたい成分の遺伝子を挿入して発酵させると、微生物が小さな工場となり、私たちが牛や鶏から摂取している乳タンパク質や卵白タンパク質など、必要な栄養を生産してくれるのです。海外では次世代の代替タンパク質の研究開発分野で、精密発酵とならんで、バイオマス発酵や伝統的発酵の研究が進んでいます。
※食分野の課題を解決するために、AIやIoTなどの最先端技術を活用した商品やサービス、技術の総称。
関連コラムはこちら

広がりゆく取り組み|1/15はフードドライブの日https://econews.jp/column/sustainable/10649/
(サステナブルノート2024.01.10)

みんなで食べる幸せを 10月16日は世界食料デーhttps://econews.jp/column/sustainable/10051/
(サステナブルノート2023.09.27)

SDGグローバル指標 2: 飢餓をゼロにhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal2.html
発酵技術で未利用資源をアップサイクル!

発酵技術は循環型社会の構築をめざす取り組みにも利用されています。とあるスタートアップ企業では、休耕田や食品・飲料残さといった未利用資源を独自の発酵技術で価値ある素材や新たな商品へと再生するアップサイクル事業を行っています。発酵技術を使った原料開発力を強みに、米やリンゴのしぼりかすなど30種の未利用資源からバイオ素材を製造し、約100の商品を生み出しました。なかには大手企業と協業し、焼きおにぎりから除菌ウェットティッシュをつくるという取り組みも。規格外の焼おにぎりを原料として発酵・蒸留させ、エタノールにするのです。発酵・蒸留の段階で発生した発酵粕は鶏の飼料になり、ゴミも出ません。将来的にこうした取り組みが大きく進めば、地球温暖化の大きな原因となっている化石燃料、そのなかでも石油に依存しない素材が増えていくでしょう。
関連コラムはこちら

まだ楽しめる元気な花を廃棄⁉「ロスフラワー」を救おう
https://econews.jp/column/sustainable/9238/
(サステナブルノート2023.07.26)

今、話題です!「アップサイクル」をご存じですか?
eco-tatsujin.jp/column/vol210_r.html
(達人コラム2022.1.25)
地球にやさしい持続可能な発酵技術

そのほかにも発酵技術はさまざまな分野で活用されています。市場規模で一番大きいのが医薬品製造分野。「抗生物質」には抗がん剤、抗細菌剤などがあり、がん細胞やウイルスを体内からなくすための医薬品で、感染症にもっとも有効といわれています。化学製品製造分野では食品添加物の製造をはじめ有機酸(乳酸、クエン酸、リンゴ酸)が微生物を利用してつくられています。また、生活用品分野では発酵でうまれる「酵素」を利用して洗剤をつくります。幅広い分野で発酵技術が活躍し、その技術力は進化しているのです。
生態系の成り立ちには、微生物の働きが大きくかかわっているため、持続可能な社会を維持するには発酵作用が必要不可欠です。排水の浄化、生ごみの資源化、病気の診断・分析、代替エネルギーとしての活用など活躍の場は広がります。自然由来で地球にやさしい発酵技術のさらなる研究開発に期待が集まります。
関連コラムはこちら

世界湿地の日(2月2日)に考える、身近な湿地と環境保全
https://econews.jp/column/sustainable/10750/
(サステナブルノート2024.01.24)

SDGsグローバル指標 7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal7.html
関連動画
製造過程で出たものをゴミにせず再利用する企業はこちら!
【第58回】たまごや工房

電気に関する総合サービスを提供する日本テクノの広報室です。エコな情報発信中。