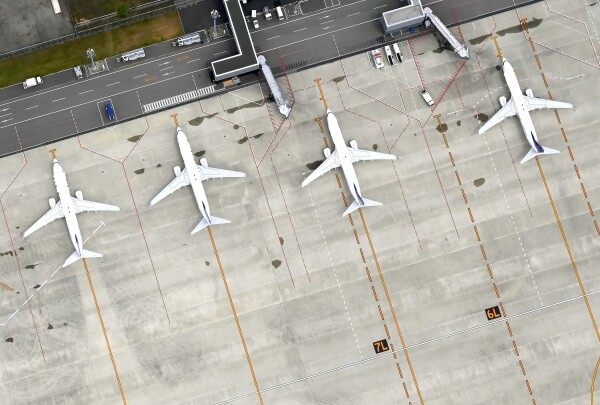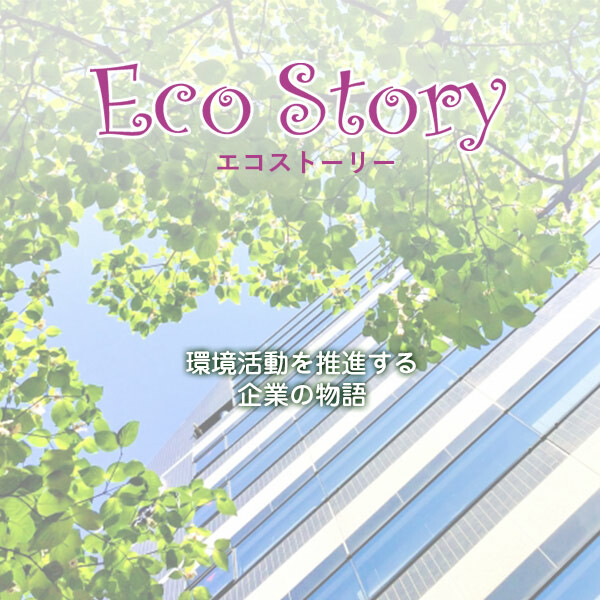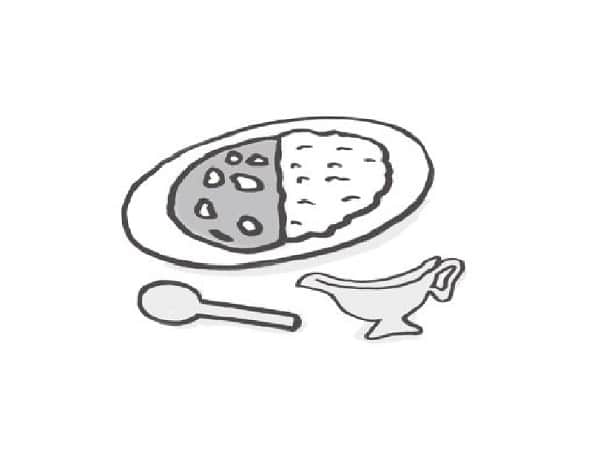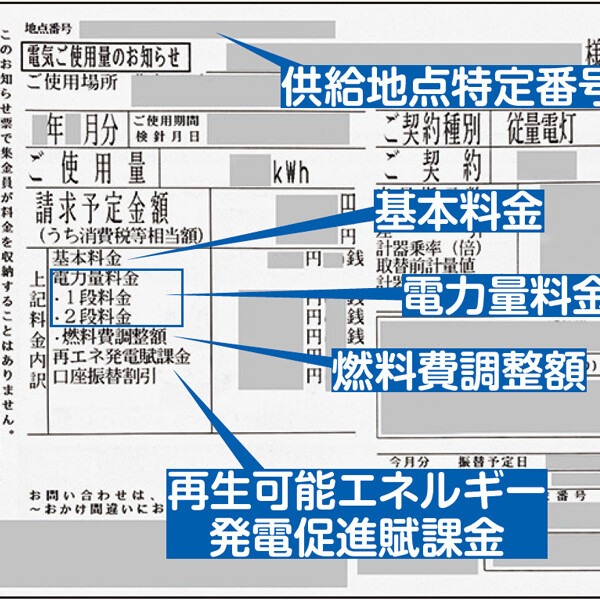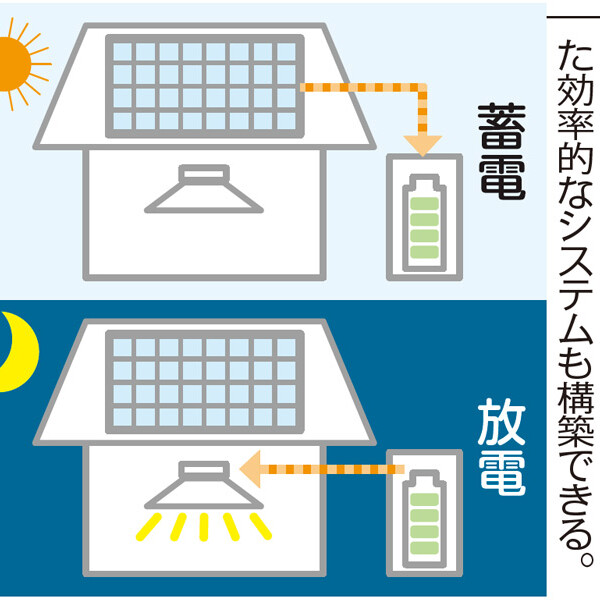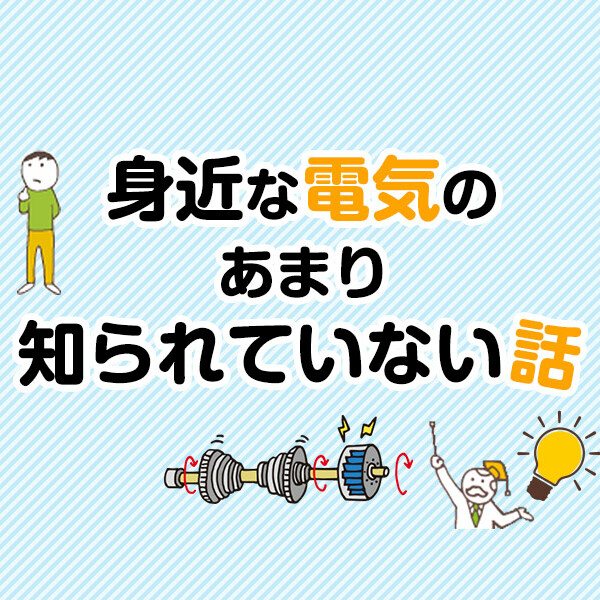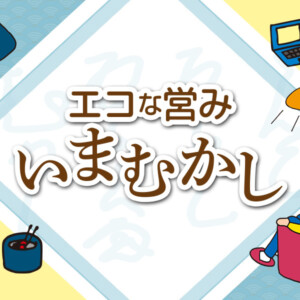奉公人、仕着せ…江戸の働き方
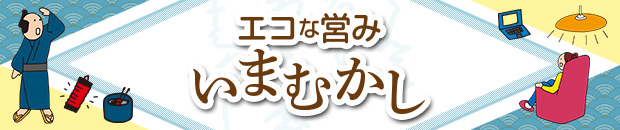
4月になり新年度が始まった。今年から新しく社会人として会社勤めする人もいるだろう。職人文化で今でいう個人事業主の多かった江戸では人々はどのように働いていたのだろうか。「エコな営み」からは少し離れるが、転勤や異動も増えるこの時期に気になる「働き方」の形態を今昔で比べてみたい。
江戸
江戸の町には米屋、漬物屋、呉服屋、傘屋、金物屋などさまざまな見世・お店が存在した。その多くは家族で経営するか個人で生計を立てているのが基本で、現代の企業のような縦型の組織に所属して働く人は武家くらいだった。
庶民が雇用されて働くことを「奉公」、働く人を「奉公人」と呼んだ。奉公人には、商家で、炊事・洗濯などの家事や雑用をする人から支配人として経営の一端を担う者までいた。生涯そこに雇用される終身奉公、年数や期間を決めての年季奉公、日雇いの日傭取りなど雇用期間もいろいろあった。一人前の職人になるために親方のもとで弟子として働きながら技術を身につけるのも奉公の一種だ。
労働に対する考え方は「住んでいるコミュニティのみんなのために働き、生きていくために稼ぐ」という意識が強かった。関東一帯の農村、雪国の人も農業の閑散期となる冬に江戸の街まで稼ぎに出てきた。
奉公人には年2回、正月とお盆に休暇があり、商家ではこのとき「仕着せ」といって奉公人への着物の支給があった。住み込みで働く奉公人が、少しでも身ぎれいにして実家に帰れるようにという配慮が込められていたようだ。
そしてこれが現代のボーナスの起源になったといわれている。
現代
明治以降の近代化でモノが量産できるようになり、工場の操業に労働力が割かれるようになると江戸時代のような職人や店は廃れてしまい、会社に勤めるという働き方をする人が多くなっていった。
今は労働時間が1日8時間と定められ、働く理由も〝生きるため〞から〝より良い毎日を送るため〞にシフトしてきて、ウェルビーイングという言葉をよく聞くようになった。自宅に居ながらリモートで業務を進める働き方もできるようになっている。
考えると、働き方は社会や科学技術の進歩に合わせ変わりゆくものなのだろう。江戸から今への変化はわかった。この先どんな様相をみせるのだろうか。