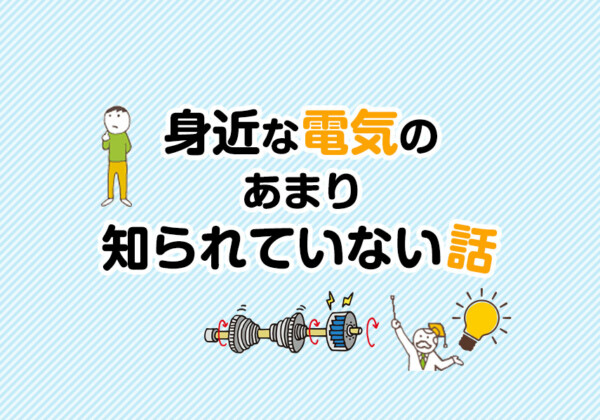
電気製品についている 「PSEマーク」とは
知っているようで、よく考えてみると深くは知らない電気の話。第10回は電気製品に仕様項目などと一緒に表示されているマークについて。...
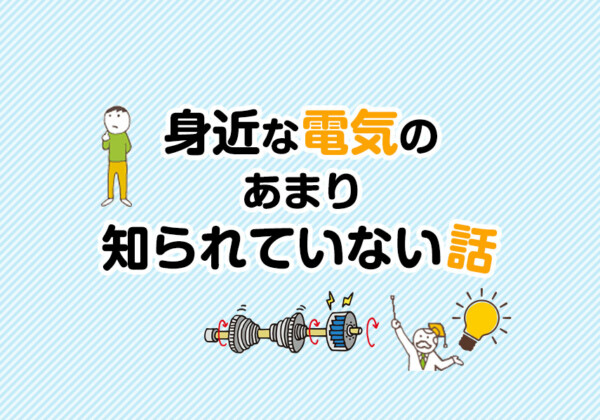
知っているようで、よく考えてみると深くは知らない電気の話。第10回は電気製品に仕様項目などと一緒に表示されているマークについて。...

出題範囲は環境市場新聞61号の掲載記事 Q1 2016年5月、地球温暖化対策推進法に基づいて政府が閣議決定した温室効果ガスの削減...
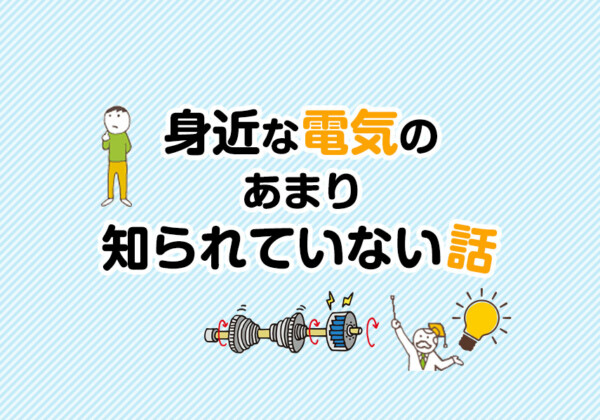
停電が起きるとまずブレーカーを確認し、落ちているレバーを機械的に上げるという人は多い。だがその前に必要なのは、ブレーカーの役割を...

出題範囲は環境市場新聞60号の掲載記事 Q1 2019年11月に環境省と国立環境研究所が速報値として公表した2018年度の国内温...
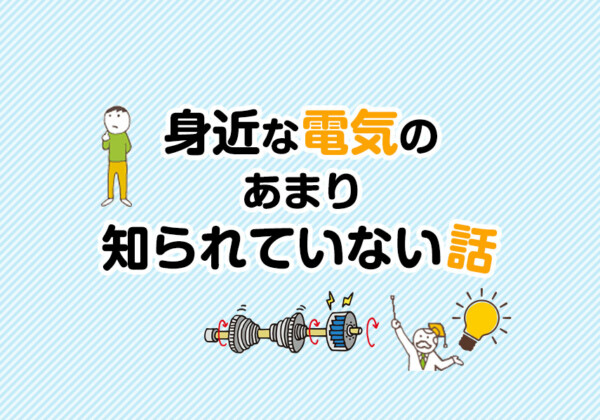
街の景色の一部になっている電柱。実はこういった風景は日本ならではで、他の先進国では電線を地中に埋め、地上に架設しない方法が主流に...

好評連載「テッくんのQ&Aコーナー」。今回からはテーマを新たにして電気に関連する資格について解説していく。 (環境市場新聞61号...

エコニュースの更新情報やメルマガ読者限定のコンテンツ、環境市場新聞発行のお知らせ、省エネ、エコに関する話題などをお届けします。

出題範囲は環境市場新聞59号の掲載記事 Q1 略称はIPCC。1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により...
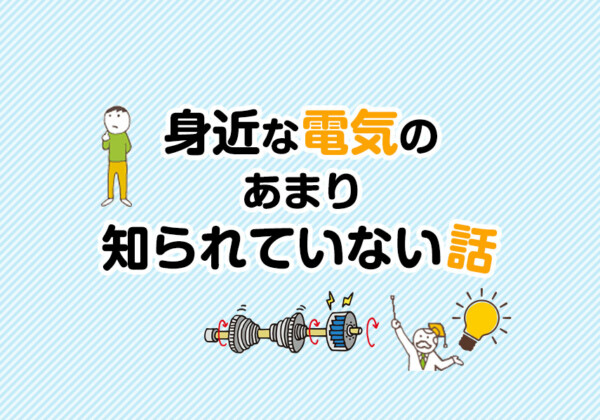
今回は電気が生まれてから手元に届くまでの経路を紹介しよう。 電気は発電所でつくられる。発電所でつくられた電気は、途中で送電ロスを...

出題範囲は環境市場新聞58号の掲載記事 Q1 経済産業省が「CO2を炭素資源として捉え、これを回収し、多様な炭素化合物として再利...
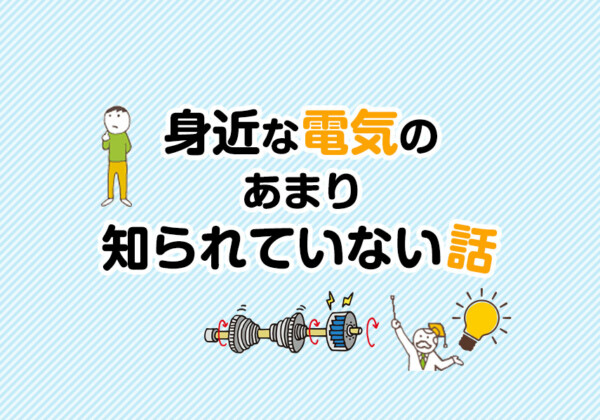
海外旅行の際、スマートフォンの充電用などに変換プラグを持参する人も多い。コンセントの形状、流れている電流や電圧の安全基準は国によ...

出題範囲は環境市場新聞57号の掲載記事 Q1 略称はWMO。世界各国の気象業務の調和を図り、推進させていく役割を担う国連の専門機...
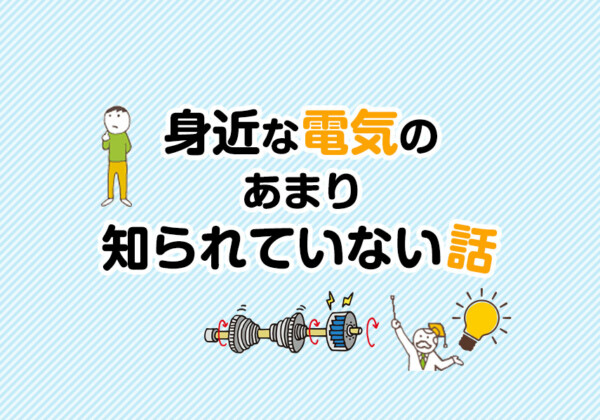
人体に電気が流れることを「感電」という。静電気でバチッとしびれを感じるのも広い意味で感電の一種だ。 大地に電気が流れ込むことを地...

希望される皆さまに無料で送付しております。お気軽にお申し込みください。
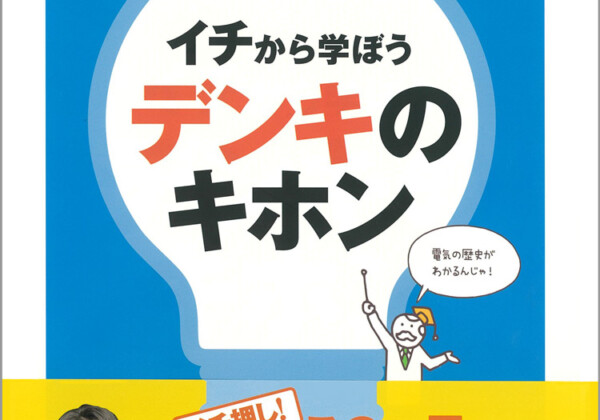
日本テクノが事業として取り組んでいる「電気」について、理解を深めていただきたいとの思いで出版しました。本書では、電気の基礎から少...

出題範囲は環境市場新聞56号の掲載記事 Q1 2018年12月、ポーランドのカトウィツェでCOP24と呼ばれる国際条約の締約国会...
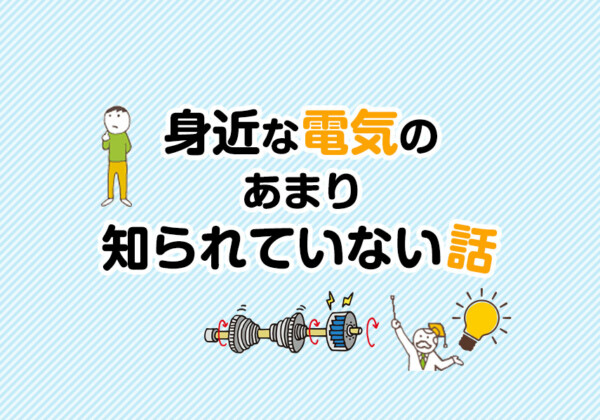
前回は電気の「直流」「交流」の違いと、現在、発電所から送電される電気はほぼ「交流」であることを紹介した。その送電で使う電線は、電...

テッくんのQ&Aコーナー。今回は再生可能エネルギー(再エネ)について解説していく。 (環境市場新聞57号~60号に掲載) Q ...

出題範囲は環境市場新聞55号の掲載記事 Q1 正式名称は「気候変動に関する政府間パネル」。地球温暖化についての科学的評価を担当す...
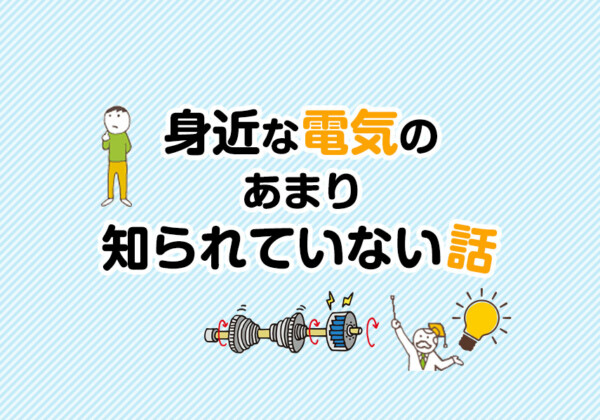
方向は一定? それとも入れ替わる? 私たちの身近にある家電製品の電源は、電池かコンセントの2つに大別できる。電池にはプラス・マイ...
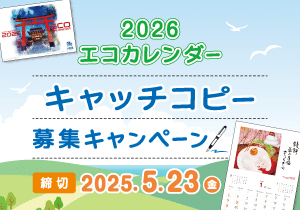
エコカレンダー2026 キャッチコピー募集キャンペーン!

Q1 2018年6月に改正法が可決・成立した「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の略称として一般的に使われているものは? ...
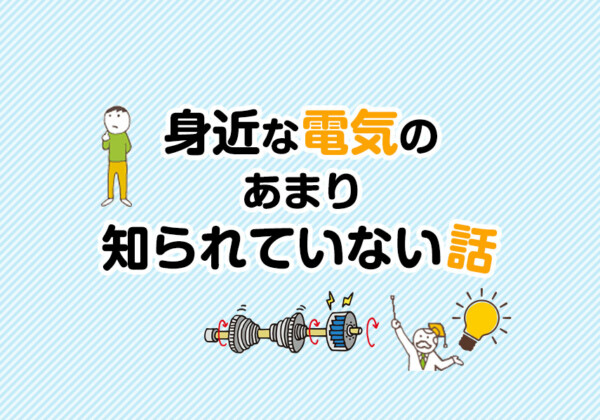
電気はその性質上、貯めることが困難だ。電気の貯蔵法はバッテリー(蓄電池)を利用するか、あるいは電気が持つエネルギーを位置エネルギ...